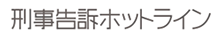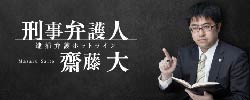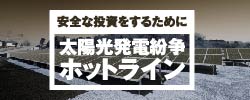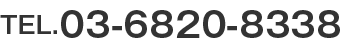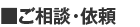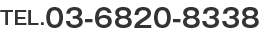1:告訴状の作成
警察署長宛の告訴状の作成は,弁護士も司法書士も行政書士もやれます。
(1)行政書士は,行政書士法第1条の2により司法警察員に提出する告訴状の作成を報酬を得て業とすることができます。ただし、検察庁に対しての告訴状は除かれます。
※行政書士法 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(2)司法書士は、行政書士の作成する告訴状の範囲から除外される検察庁に対する告訴状の作成を報酬を得て業とすることができます。
(3)弁護士も(2)の司法書士と同じです。
2:弁護士に頼んだ方が良い理由
端的に述べると、告訴状の作成をして依頼人に渡すだけでは告訴受理やその後の手続が難しいからです。
これまでにお話したように、真に捜査して加害者を検挙して欲しいという事案で、最初から告訴状を作成して提出することは実務上ほとんどなく以下の作業が欠かせません。
(告訴受理前)
警察との交渉・連携
警察から指示のあった資料の収集
警察の指摘を踏まえての犯罪事実一覧表の作成や修正など
(告訴受理後)
警察との交渉・連携
検察官との協議・相談
場合により加害者の弁護人が持ちかけてくる示談交渉の対応
加害者が立件されたとの加害者への損害賠償請求や訴訟提起
(不起訴になった場合)
不起訴であっても加害者に対する民事訴訟の提起
不起訴を不服とする検察審査会への不服申立
このように、告訴状を作成して交付されただけでは,足りないのです。
また,進展によってやることは多岐にわたってくるので、検察官との交渉や加害者側弁護士が持ちかけてくる示談交渉を行政書士や司法書士に依頼しても受けられないので、弁護士に依頼することが理にかなうものと言えます。
3:告訴状の作成だけを頼むのが良い場合
事案が明確で受理は間違いない場合にそういうこともあると思いますが、そういうこと自体が少ないでしょう。
むしろ、親告罪の場合に、そういった事案でしたら、警察が告訴状の記載部分 を 作成し、そこに告訴人となる被害者が署名押印をすれば良いという形式の書類を用意してくれることのほうがあり得るのではないかと思います。そのような告訴状は刑事弁護の公判弁護活動において複数目にしたことがあります。